
今回、「川のある町」としてお邪魔させていただいた場所は、市街地の中央に槻川が流れる小川町です。パソコンで作る音楽講座が無料で開催されることになった2024年12月から約1年をかけて、初めてパソコンでの音楽制作に取り組ませていただきました。
前半の記事でもご紹介させていただいた、(株)SGN代表取締役、脇元寛之さんが主催されたパソコンで作る音楽講座は、2011年に閉校した上野台中学校の再利用プロジェクトのひとつとして開催されることになり、初級と中級の2クラスに分けて全部で6回の講座で実施されました。中級クラスで参加した私は、講座を受講させていただくことで、生まれて初めてパソコンで音楽を作ってみました。その音楽をコチラで公開させていただきます。
講師の脇元寛之さんにもお願いして、今回作っていただいた音楽もご紹介させてください。脇元さんのプロフィールやご自身の音楽制作についての想いなどが、「川のある町と音楽」(前半)に掲載させていただいておりますので、下記URLから是非ご覧ください。


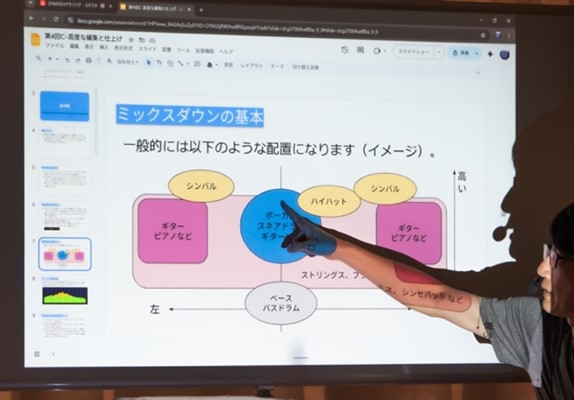
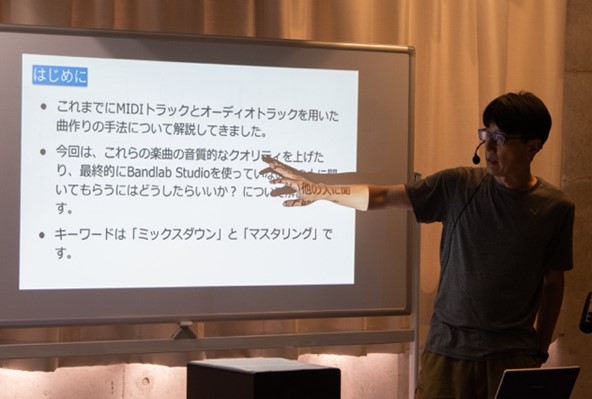
今回の音楽制作は、クラウドアプリ「Bandlab」(無料)をノートパソコンにセットアップして制作しました。初めて体験するパソコンでの音楽制作だったので、楽器も弾くことがあまり得意ではない私は、録音に関しての講座を受けるうちに、町の音を録音して音楽を作りたいと思うようになりました。
そして小川町を歩きながら私が録音した音は、川の流れる水の音や、その時に聴こえてきた鳥の声、そして偶然にもその時に重なるように流れてきた、ちょうど正午の時刻に流れて来る町の音楽でした。
歩きながらスマホで写真も撮り、歩く速さに合わせて流れてくる音と景色に、楽しみながら心を寄せることが出来ました。そして集めた音をパソコンに入れて、1分くらいの音楽を作ることを目標にしました。
いくつか録音した川の音をひとつずつ再生しながら、使いたいと思う音を選んで、その音に正午に流れた町の音楽のメロディを重ねてみました。
実際に録音した正午の町のメロディーが1分間もなかったので、音の速さを少し遅めに再生しながら音の長さを調節すると、ゆっくりと流れるそのメロディーが、さらに心地いい音に感じられて来るのが不思議でした。

最後に鳥の声を録音した音を重ねてみました。1分間の中で一定に鳴き続けるわけでもない鳥の声が、とても自然なリズムに想えて来て、そんなリズムがもうひとつ欲しくなった私は、家にあったカリンバという楽器で、ランダムに音を弾いてそれを録音してみました。
槻川の音、町に流れる正午の音楽、鳥の声、カリンバの音。今回はこの4つの音で音楽を作ってみました。川の音を再生してみると、風の音や車の通る音も聞こえてくるので、町の音がいくつも静かに重なり合いながら、今回の町の音楽が作られていくということも、知ることが出来ました。

初めてパソコンで音楽を作るという今回の機会で、町を歩きながら音を拾い、歩く速さの中で感じる一期一会の町の音というものに、あらためて意識を向けることが出来ました。
そして歩きながらスマホで撮った写真にその音楽を重ねて、もうひとつの時間軸を作ってみました。もしよろしかったらご覧ください。
生まれて初めて作る音楽がどうにか着地出来ましたが、講座を受けて行く中で自分では音楽を作ることが出来ないかもしれないと弱気になり、講師の脇元寛之さんに小川町を流れる川の音を使って、音楽を作っていただくことをご相談してしまいました。
そして快く了解していただいた脇元さんに作っていただいた音楽と、作られた音楽に関してのコメントもいただいておりますので、是非こちらでご紹介したいと思います。
脇元さんに作っていただいた音楽はこちらです。
曲名:「Water of September」
この音楽に関する、脇元さんのコメントです。
「川の水の音と楽器の音を組み合わせて作りました。槻川の音と、風布川の音が混じっています。よく聞くと、川で遊んでいる子供の声も入っています。自分で弾いたアコースティックギターの音も入っていますが、アコースティックになりすぎないように、電子楽器の音も入れました。
一般的には「アコースティック=自然」というイメージで、都会を離れて音楽活動をするにはアコースティックでなければ、という考えに陥りがちです。しかし、自然に恵まれた地で生活するということは必ずしも、自然だけを大切にするということではありません。
私たち人間が自然の中で共存するということは、人間の作り出した技術と無垢の自然の間のどこかで、折り合いをつけながら生きていくということです。自然の音と電子の音はどのように融和するのかというのが、僕の作る音楽の現在のテーマなのかもしれません。」

「自然の音と電子の音の融和」という言葉が、とても深く心に響きました。
音と音が織りなすことで生まれる新しい音楽の融和が、そこにはあるのかもしれません。脇元さんが音楽を作られる上で、向き合われている現在のテーマまで語っていただけたことに、心から感謝しています。パソコンで音楽を作る講座に参加させていただいて、あらためて耳を澄まして、町を感じながら歩くことが出来ました。音を集めて作る時間軸には、過ぎた時を振り返りながら、また新しく歩き出してもいるような、不思議な新鮮さがありました。どうもありがとうございました。
「川のある町と音楽」このテーマを持ち寄って、今回は小川町を訪ねて音楽を作るという体験も、させていただくことが出来ました。
前半と後半、2回の記事連載でご紹介させていただきましたが、もしご感想などいただけたら嬉しいです。こちらのメールアドレスからお送りください。
町の音に耳を澄ますことで、あらためて感じることがあります。そこに暮らすことで関わることの毎日の時間が、あらゆるモノたちとの成り立ちで、時に新しい時間軸が作られるということ。
息を吸うようなあたりまえなことが、ひとつ意識を足すことで新しい気付きとなるということに、この音楽制作を通じてとても新鮮に感じることが出来ました。
「暮らす町の音」というのは、どこに居てもあります。
そんな音たちを集めて住む町の時間を、そして毎日の暮らしを振り返ってみるのも、面白いと思いました。今回の機会を始まりとして、町の音楽を作ってみる楽しさを味わっていけたらと思っています。
今回の記事を読んでいただきまして、どうもありがとうございました。
この機会を与えてくださった方々に、槻川の風景を最後に添えながら、心から感謝の気持ちを込めて、どうもありがとうございました。

写真&文
平野晋子(ひらのくにこ)
フリーランスフォトグラファー&ペンネーム星日ト 奏(ほしひと そう)で、ショートストーリーを書いています。受賞歴有り。毎日の暮らしの中で、ちょっとした風景を記録するのが好きです。


.png)




